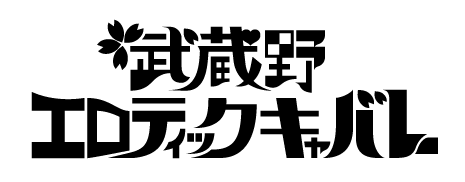お兄ちゃんが高校生になってから、周りにきれいな女の人が増えた。
大人っぽくて、体のラインも女性的で、おしゃれで、セクシーで。
そんな素敵な女の人に囲まれているお兄ちゃんは、違う人みたいだった。
男の人、だった。
ああ、私はこのままじゃいけない。
昨日までとは違う私にならなくちゃ。
大人っぽくて、色っぽくなって、私のことを視界にいれてもらわなきゃだめ。
私のことを女だって感じてもらわないとだめ。
ファッション誌をみて研究した、セクシーな女になるためのお洋服。
ホルターネックのキャミソールはちょっと濃い目のローズピンク。
裾広がりになっていて、サイドあしらった透け感のあるシフォンジョーゼットでちょっとセクシーに。
同年代と比べたらいささか大きめなヒップは、あえてラインを出すことで視線を釘づけ。
女の子を一番かわいく見せてくれるカーマインレッドのタイトミニ。
お化粧だって勉強したわ。
マンダリンオレンジの頬に、アイシャドーは恥じらいラメ入りピンク。
リップグロスをたっぷり塗って、ほてるくちびる。
ちょっと派手かしら。
でも、このぐらいしなくちゃ、お兄ちゃんをどきっとさせられない。
「ヒカリ、その服どうした?」
私がこの服を見せたとき、お兄ちゃんは眉根をよせていた。
どうしよう、似合ってないのかしら。
「買ったに決まってるじゃないの」
「そうじゃなくて!」
なんだか悲しそうですらあるお兄ちゃんの顔をまじまじと見てしまう。かわいい。
「だって男の人はセクシーな方が好きなんでしょ?」
お兄ちゃんがおっぱいのおっきな人の雑誌とか読んでるの、知ってるもの。
そこまで色っぽくなれなくても、私だってお兄ちゃんの好みに近づきたい。
「似合ってないぞ」
ああ、やっぱり。自分だってわかってるわ。
私まだこどもなんだ。
だって今、現に頬を膨らませてお兄ちゃんの胸のあたりをこぶしでぽかぽかたたいている。
「もっとおとなになりたいの」
もっともっとおとなになって、きれいになって、お兄ちゃんの隣を歩きたい。
恋人だって間違われたい。
だけどお兄ちゃんに似合ってないって言われたのがショックで。
うそで固めた私を見透かされてしまったようで。
「おとなになることは、セクシーな服を着ることじゃないだろ」。
ごもっともだわ。見た目ばっかり気にしたって、私の中身はまるでおこちゃまだもの。
「お前にはもっと可愛い服が似合うよ」
ケープでまとめた髪をあったかい手がくしゃくしゃにする。
このおひさまみたいな笑顔にいつもやられちゃうんだ。
お兄ちゃんがそういうなら、着ます、かわいい服。
着替えてくるねとぽそぽそ言うと、ほっとしたように眉毛を下げた。
「着替えたら、一緒にお買い物、行ってくれる?お兄ちゃんにヒカリの服、選んでほしいの」
「ああ、行こう」
やったあ。デートだ。
ばかだわ。私、なんで男の人が好きな服装なんて漠然としたものを求めていたのかしら。
男の人じゃなくて、お兄ちゃんの好みじゃないと意味ないじゃない。
もっとかわいい服が似合うんだって、私。うれしいな。
うきうきしながらワードローブをひっくり返す。
これにしよう。清楚なエンジェルブルーのAラインワンピース。
襟と袖にステッチが入っていて、私の一番のお気に入り。
おっと、服を着る前にお化粧を落としましょう。
まぶたにのせた熱情を拭うと、濡れたシートににじむ、さっきまでの泣きそうな私。
洗面所でしっかり顔を洗うと、前髪から水滴がこぼれた。
鏡に映る14歳の私はおとなじゃないけれど、今はそれでもいいの。。
お化粧しても派手な服を着ても、おとなのように色っぽくはなれない。
でもそれでいいんだわ。無理することなんかない。
部屋に戻ってお気に入りの服に袖を通す。
ウエストをリボンで結び、スカートのひだを整える。
さっきまで泣きそうだったのがうそみたい。
仕上げに、ダイヤ型のピンクの小瓶に入ったベビードールを空中に吹き付けてひとくぐり。
このぐらいの背伸びは許してね。
「行こう!」
玄関のドアを開けると、熱気と日差しに眼がくらんだ。
はやくはやくとせかすふりをして腕を組む。
お兄ちゃんの腕は結構筋肉質で、ちょっと固くなったところをきゅっとつかんで撫でるのが好き。
「なんだかデートみたいだね」
もう私、自分に嘘はつかない。無理しないことにするわ。
ねえ、だから。
大好きよ。お兄ちゃん。
#八神兄妹版深夜の真剣お絵描き文字書き60分一本勝負
2015/5/22 お題自由