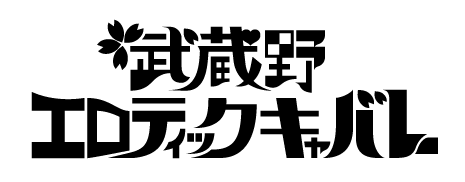部活が終わってから携帯を見ると、メールが1通きていた。
差出人は、八神太一。
ぐらぐらと足元から崩れてしまいそうな気持ちを抑え、ゆっくりと制服に着替える。
早くメールを見てしまいたい、いやむしろ決して見たくない、などと悶々考えていたらシャツのボタンをひとつかけ違えていた。
面倒だったのでそのままにしてブレザーに袖を通す。
太一からメールなんて久しぶりだ。
だって私たち、あの日以来会話もしてない。
悪い報せだろうか、良い報せだろうか。
何が書かれていてもきっと涙しか出ない。
家に帰ると母は出掛けているようだった。
制服から部屋着に着替え、ベッドに腰かけて携帯電話を握りしめた。
息を限界まで吸って、ゆっくりゆっくり吐き出す。
意を決してぽちぽちと携帯のボタンを押すと、光る液晶の中で黒々とした文字が鋭利な刃物で胸を刺すように飛び込んできて、目眩を覚える。
ほらね、やっぱり悪い報せじゃない。
涙が止まらない。
あの日太一はラブレターをもらったのだった。
後輩の女の子で、サッカー部の練習をよく見ていて憧れていたとかなんとか。
空、俺、どうしよう。
彼は私に相談しにきた。件のラブレターを持って。
「全然知らない子なんでしょ?」
「ああ」
「どんな子か知らないんじゃアドバイスのしようもないわよ」
「そりゃあそうだけどさあ」
太一は珍しく動揺している。
16年生きてきてはじめてもらったラブレターを目の前に、難しい顔をしてうなっている。
「空はラブレターとか書いたことないのかよ」
バカ太一。
「ないわよ」
「頼りにならねえな」
「悪かったわねえ」
そのラブレターの主に、私は心当たりがある。
『八神先輩とどういう関係なんですか』
真っ赤になってぷるぷる震えながら、か細い声で問い掛けられた。
瞳はゆらゆらとうるみ、拳を胸の前でぎゅっと握りしめながら、それでも強さを伴ったまなざし。
私のことをそんな目で見ないといられないほど、この子は太一が好きなんだわ。
『恋人同士なんですか』
『違うわ』
少女はほっとしたように笑い、ありがとうございましたと言って友達の方に駆けていった。
きっとあの子なんだろう。
大人しそうで、儚くて、可愛らしい、女の子らしい女の子。
「いいじゃない、付き合ってみれば」
「お前そんな簡単に…」
「じゃあ断ったら?」
意地悪をしているんじゃないの。自分でも何て言えばわからないの。
一番言いたいことは言えないの。
今ここで私が太一に好きだって言うのは、フェアじゃない。
私は想いを伝えることをずっと怠ってきた。
太一の「親友」の立場を利用して、ずっと居心地の良い場所で過ごしてきたから、あんなふうに何もかもを振り絞って想いを紡ぎ出す彼女に胸を打たれた。
私はなんてずるいんだろう。
恋はあせらず、だけど早い者勝ちだ。
彼女はラブレターを書くことで、舞台に登った。
一方私はまだ楽屋を出てすらいない。
それなのに、今まさに舞台に引き立てられようとしている太一を舞台袖で止めるような真似をしてはいけない。
ハッピーエンドにするかどうか、決めるのは太一だ。
「とにかく、会ってから考えてみたら?」
二週間もたてば、サッカー部の練習が終わった後に、肩が触れ合うくらいの距離で歩く二人の姿をよく見かけるようになった。
それきり太一とは話をしていない。
私は走った。泣いた。走った。泣いた。泣いて走った。涙を乾かすように。
どうして今さらそんなこと言うの。
太一は私にどうしてほしいの。
私の恋はあの日に終わった。終わりにしようと決めた。
私は舞台にも立てなかった。
想いを伝えた人にしか寄り添う権利はないの。
恋は早い者勝ち。
彼女が行動を起こすまで、太一に告白しようなんて思ってもみなかった。
ずっと一緒にいられるものだと信じて疑わなかった。
この世の春のような笑顔で頬を染める彼女を目の当たりにした時、心に刺さった棘からじわじわと血が滲み出した。
私はきっと太一の特別だった。でも特別だからって恋人になれるわけじゃない。
親友。仲間。幼なじみ。でも恋人じゃない。
私は太一を避け続けた。
太一は私が気をつかってると思ったのか、それとも彼女の方に何か言われたのか知らないが、別段話しかけても来なかった。
あのとき、なりふりかまわず太一に告白していたらよかったのかしら、いやいやそんなこと考えちゃいけないわ、だって太一はあの子と幸せなんだから、って何百回も考えて、考えに考えた結果、何も言わずに諦めて、苦く美しい青春の思い出にしようと決めたのだ。
なのに今さらわざわざそんなこと言ってどうしたいの。どうしてほしいの。
なぐさめてほしいのか、それとも。
太一は私を好きじゃない。仲間だって、親友だって思ってる。そんなことわかりきってる。
だってあの子にしているように、目を細めてはにかんだり、薄い紙を一枚隔てているみたいに手をつなぐなんて、私にはしない。
どうしてさっさと幸せになってくれないの。
どうしてさっさと諦めさせてくれないの。
私はどうしたらいいの。
_____________________________________________
From : 八神太一
To : 武之内空
Subject : 無題
あいつと別れた。
やっぱりお前と一緒にいるのが一番いい。
_____________________________________________
私は走った。公園を抜けて海に出る。
夕陽が沈む直前の、半分橙色で半分紺色に染まる空を見上げて、また涙がこぼれた。
身体中の水分と言う水分全てが目から溢れてからっぽになってしまう。
いつの間にか濃紺は橙を覆いつくし、空にはちいさな星がきらきらと光っていた。
いつかこの涙が止まるとき、私はまた恋をするんだろうか。
これは、彼とずっと一緒にいるための、親友になるための儀式。
「ずっと太一が好きだったの」
最後の台詞は海風にかきけされて幕が下りた。