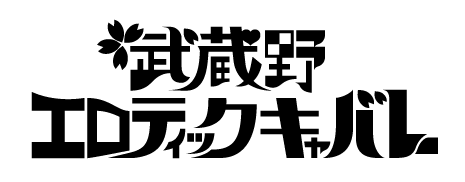キャンディやチョコがあっても出さないで 欲しいものならわかってるでしょ
「お兄ちゃん、なにかあまいもの、ちょうだい」
学校から帰ってきた俺の後ろをぱたぱたおっかけて、ヒカリは部屋に入ってくる。
「お菓子くれないとなんとかってやつか」
今や大体どんな店もかぼちゃやらなんやらの飾りつけをしている。
ここ数年でよくもまあこんなに浸透したもんだ。
「ねえ、なにかあまいもの、ちょうだい?」
ジャケットとシャツをぽいぽい脱いでその辺に放る。肌寒くなってはきたが、自転車をこいでいればまだ汗ばむくらいだ。
やっぱりTシャツがいちばん動きやすい。
「お菓子なんて持ってねえよ」
「べつにお菓子がほしいなんて言ってないじゃない」
「なんだよそりゃ」
ベッドに腰かけて、俺の枕を両腕でぎゅっと抱いて、ルビーの瞳を光らせる、俺の小悪魔。
「なにかあまいもの、ちょうだい?」
薄いくちびるで妖艶に笑う少女のまなざしは、いつだって俺を逃がしちゃくれない。
俺が腰かけると、ベッドのスプリングがきゅっと鳴った。
俺たちの間には沈黙だけが佇んでいる。
音をたてずにくちびるに触れ、離し、食み、味わう。
しっとりと熟れていく頬の熱を冷まさないように両手で覆った。
ヒカリの手が俺の背中をぎゅっと掴む。
「これでいいか?あまいもの」
上唇をなぞりながら吐き出した声を感じて、ヒカリはぴくんとつまさきを伸ばした。
「全然足りないわ」
ぎゅうっとくちびるを押し付けながら言葉を吐息に混ぜる。
「足りないから、いたずらしちゃう」
吐息と衣擦れが沈黙に落ちてくる。
ふとんをかぶって、音も光も遮断して、ふたりだけしか感じられない甘いいたずらの時間だ。