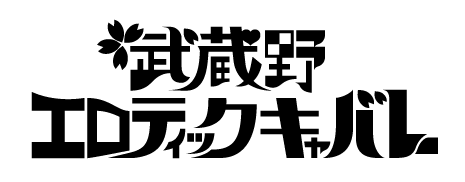宝石を濡らさぬように 春情を閉じ込めた箱 捨てられねえよ
「今夜は一緒に寝てもいい?」
お兄ちゃんはもうベッドに入っていた。
あたしは自分用の枕をぎゅっと握りしめ、絞り出すように声をかけた。
春の夜空に溶けて消えてしまいそうな声。
暗くてお兄ちゃんがよく見えない。
今どんな顔してるの。どんな気持ちでいるの。
裸足の指先から全身が冷たくなっていく。
「いいよ」
吐息交じりのあたたかい声にうながされ、あたしはお兄ちゃんのベッドにお邪魔した。
お兄ちゃんは真ん中から少しずれてあたしを迎え入れてくれる。
さっきまでおにいちゃんがそこにいたぬくもりをあったかいお布団から感じ取って、 ふいに涙が出そうになる。
その存在を確かめたくて、お兄ちゃんのパジャマの胸元をぎゅっとつかんだ。
「もうすぐ高校生だってのに、そんな甘えん坊で大丈夫かよ」
あたしの頭にぬくもりがふれる。それはあたしの体のなかで何倍もの熱に増幅している。
「だいじょうぶ、だもん」
音になりそこなった吐息があたしたちの間を抜けていった。
お兄ちゃんのつま先があたしの足の指をつんとはじく。
「またこんなに足元冷やして」
あたしの足にぬくもりがふれる。それはあたしの体のなかで何倍もの熱に増幅している。
そして行き場を見つけられずに、からだの奥の奥にためこまれていくのだ。
「だってこの部屋寒いんだもん」
びっくりするほど片付いた部屋。
からっぽの箱の中で、このベッドだけが生物のように熱を持っている。
なんにも、残していかないのね。
「ねえお兄ちゃん、これ、もらっていい?」
「なんだそれ」
荷造り用の麻ひもの切れ端だろう。ベッドサイドに転がっていた。
「それはごみじゃないのか」
「ごみだねえ」
だけど唯一、この部屋に残されたお兄ちゃんのかけらでもある。
あたしはそれを左手の、小指にきゅっと結んだ。
薬指には結べなかった。結ばれなかった。
「おにいちゃん、一人暮らしなんかしたら、さみしくなっちゃうよ」
声が上手にだせない。のどの奥に思い出がつまっている。
「たまには、帰ってくるさ」
お兄ちゃんはいつも夏みたいに笑う。からっとして、まぶしくって、胸があつくなる。
だけど今あたしの目の前にいるお兄ちゃんは、春のように笑う。
霞のなかでゆっくりと死を待っているようで、あたしは胸がしめつけられる。
#八神兄妹版深夜の真剣お絵描き文字書き60分一本勝負
2016/4/22「春」