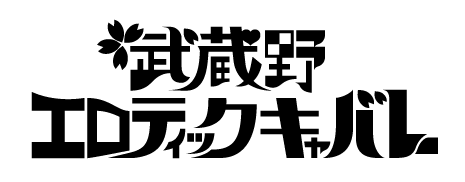ミーミルの泉に咲いた白い薔薇
つい5分前までベッドに腰かけて談笑していたはずが、なだれ込んだら一瞬だった。
ちょっといつもより深めのキスをして、彼女の髪が僕の手に絡んできた、ただそれだけ。
BGM代わりにかけていたクラシックのCDがリストの「ためいき」を流し始めたころには、彼女は僕とベッドの間に転がっていた。
「ミミさん、あの、」
自分は理性で生きているのだと思っていた。
いたずらに彼女を傷つけたりなんかしないと。
けれどほんのわずかな隙間に入り込んだ衝動は、そのまま僕の内側を燃やしてしまった。
いつもきれいにまとめている髪を乱して横たわる彼女の姿はあまりに蠱惑的だ。
「光子朗君…」
チェリーレッドのくちびるから僕の名前が紡がれる。
それは僕のからだを熱暴走させるのに十分だ。
しかし同時にこの衝動をどう処理すればいいのかがわからない。
いや、知識として理解してはいる。
アレを、ソレに、こう。
…………。
太一さんがいざというときのために、なんてふざけて置いていった小さな箱もある。
わかってはいるんだけれども。
ただ、具体的にどう動けばいいかがまったくわからない。
それ以前に彼女がそれを望んでいるのかもわからない。
瞳をうるませて頬を紅潮させながら僕を見つめる、その彼女の表情からはイエスなのかノーなのかが読み取れない。
な、情けない。
こんなところで硬直している自分に腹が立ってくる。
道筋が見えなければ一歩も進めないなんて。
「ミミさん、すみませんでした」
あくまで冷静に、焦りをみせないように態勢を立て直そうと起き上がった。
と同時に低反発の枕が僕の右頬に見事にヒットする。
「なんで謝っちゃうのよ」
彼女はノースリーブのワンピースからのびた細い肩を震わせていた。
「あのまま知らん顔で進められてもいやだけど、謝られるなんてもっといや!あたし、したくないなんて言ってないでしょ!」
ミミさんはベッドに座って、僕の枕をめちゃめちゃにしている。
「わからなかったんです。ミミさんが、どうしたいのか」
「わからないならなおさら勝手に決めつけないで」
至極もっともだ。全く僕はなんでこう他人の心の機微に対して疎いんだろう。
「そりゃちょっとびっくりしたわよ。でも、好きな男の子と、そうなりたくないわけ、ない」
枕をぎゅうっと抱きしめて顔をうずめるミミさんのことを、愛おしいと思う。
傷つけたくないだとか、ちゃんとできるかなんて、ただの自己保身だ。
だいじなのは僕ら二人の、きもちだったのに。
「ミミさん、すみませんでした」
そっぽを向いた彼女を背中から抱きしめる。
「ねえ光子朗君」
首筋からは甘い匂いがした。
「わからないなら、ちゃんときいて」
彼女は僕に向き直り、じっとみつめてくる。
鼻から息を吸って、大きく飲み込んだ。
「ミミさん、しても、いいですか」
いつもより低い声が出た。全身が熱い。
「うん」
可憐な声とともに、さくらんぼのくちびるが小さいキスをくれた。
「うまく、できないかもしれないけど」
「あたりまえでしょ。あたしたちふたりとも、はじめてなんだから」
ベッドは揺れ、彼女の華やかな髪が散らばる。
シルクのような心地よい肌が触れるたびに、びくんと正直に波を打つ。
想像をはるかに超えた刺激。脳を刺すような快感。
たまらなくてくちびるを押し付ける。額に、まぶたに、頬に、くちびるに。
甘い吐息を交換し合って、ほてるからだをぎゅっと抱きしめた。
ラベンダー色のワンピースの上からでも感じられる、ふくよかな果実。
舌をからませながら、右手でふくらみに手を添えてみる。
一瞬僕の肩を掴む手に力が入ったが、こくりと小さく頷いた。
心臓の音、布のこすれる音、肌が重なる音。
あなたにふれるために手を伸ばす。
「こうしろうくん、すき…」
「僕も、すきです、ミミさん…」
僕は今、あなたにさわりたくてさわっています。