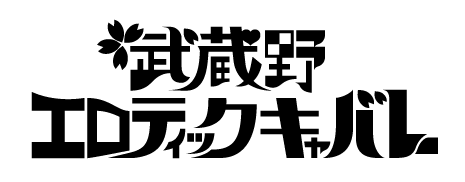まんまるい下弦の月の背徳は清く正しく心乱れる
湿気のこもった部屋でせんべい布団とブランケットにくるまりながら、あたしは今日読んだ本に出てきたことばを思い出していた。
「色のない緑色の考えが激しく眠る」
「チョムスキーか」
からだの向きをごろんと変えて、お兄ちゃんはあたしの顔を覗き込む。
「よく知ってるね」
「これでも大学生だぞ」
薄暗い部屋に白い歯が光った。
文法的には正しくても、意味の通らない言葉。言語学者のおじさんが考えた、ナンセンスな言葉。
「いろのないみどりいろの考えが激しく眠る」
「気に入ったのか、そのフレーズ」
「いろのないみどりいろってなんだかきれい」
裸の胸板に頬を寄せた。汗ばんだ肌にさっきまでの熱がまだ残っている。
「サイダーみたい色かな」
「色がないのと透明なのは違うんじゃないか」
「んもう。ナンセンスなんだからいいの」
「便利だな、ナンセンスってやつは」
「きっとね、夏みたいな色。蒸し暑い夜に狭いワンルームのせんべい布団で抱き合って、のどが渇いたなあと思ったら冷蔵庫からさっと出てくる冷えたサイダーみたいな色」
「つまりお姫様は今サイダーをご所望ってわけか」
あたしの手を取って王子様みたいに指先にくちづける。
「え、あるの?」
「いや、コーラしかない」
「じゃあ今度来るとき買ってくるね」
ふふふと笑ってお兄ちゃんの頬に軽くくちびるを寄せた。
ついこの間まで一緒に暮らしていたはずなのに、お兄ちゃんの家に泊りにくる生活に、あっという間に慣れてしまった。どちらかの部屋で布団をかぶって、声をひそめて抱き合うよりも、今は自由で安らかだ。お兄ちゃんが一人暮らしをするってきいたときは、そりゃもちろん寂しかったけど、もうお母さんやお父さんの目を気にしてこそこそ部屋を行き来しなくてもいいということに少しほっとした。
もちろん、高校生にもなって一人暮らしのお兄ちゃんの部屋に二週間に一度は泊りに行くような娘のことを両親がどう考えているか、気にならないわけではない。
お兄ちゃんに彼女ができたらどうするの、ときかれたときは、わかんない、としか言えなかった。
「ヒカリも大学生になったら、ここで一緒に暮らしたいな」
「ここで?ふたりではちょっと狭いだろ」
「狭くてもいいもん」
ぎゅっとからだを近づける。素肌と素肌がふれあって、熱がたまっていくのを感じる。
「そのときは、二人で暮らす部屋に引っ越そう」
お兄ちゃんの笑顔は、こんな薄暗い部屋でも太陽みたいだ。
胸がきゅうとなって、おにいちゃんを力いっぱい抱きしめた。
それよりも強い力で、あたしはお兄ちゃんの腕に抱かれた。
「ヒカリはお兄ちゃんが好き」
文法的には正しいことば。
「お兄ちゃんと結婚したい」
だけど正しくないことば。
「お兄ちゃんのこどもがほしい」
お兄ちゃんはあたしに正しくないくちづけをする。
「俺もヒカリが好きだよ」
正しくないくちびるは、あたしの頬を、額を、耳を、首筋を、のどを、胸を、背中を、指を、太ももを、足先を、順番に冒していく。
正しくないあたしたちは、さっきまでいた宵の淵まで戻ってきた。
あたしたちを隔てるすべてのものを取り去って、ふたたび夜に沈んでいく。
#八神兄妹版深夜の真剣お絵描き文字書き60分一本勝負
2016/3/11「グリーン(緑色)」