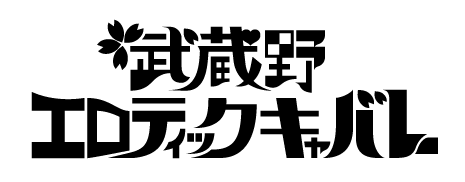はめ殺し窓に艶めく白い肌 夜景になりに今年もふたり
帝国ホテルの最上階のバーで、いつもと同じズブロッカを傾ける。
待ち合わせてはいない。ただ俺たちは毎年同じ日に同じ場所で逢う。
何時に来るかはわからない。来ないかもしれない。
大きなガラス窓からは東京の夜景が見渡せ、日常の喧騒からは別世界だ。
カウンターの中では初老のバーテンダーが滑らかな手つきでシェイカーを振っている。
ズブロッカを3杯飲んだら帰る。そう決めていた。
特に約束をしているわけではない。
来るかもしれないし、来ないかもしれない。
いっそ来ないほうがいいのかもしれない。
約束ではないなんて言い訳にすぎない。
手を放して自由を与えているようで、実際は籠に閉じ込めているようなものだ。
縛らないし、縛ってやることもしない。互いに縛られるのを望んでいたとしても。
この10年、3杯目を飲み干したことは一遍もない。
「ベリーニを」
静寂に鈴が響くような声がした。
白磁の肌にルビーの瞳。亜麻色の髪は腰までまっすぐ伸びている。
ドレッシーでクラシカルなワンピースは瞳と同じルビー色で、腰には黒いレースのリボンがあしらわれている。
妖艶さと清廉さを併せ持った、美しいひと。
ついこの間まで少女だったはずなのに、いまや立派な淑女だ。
「お兄ちゃん、待たせてごめんなさい」
俺にとってはいつまでもあどけなさの残る、ヒカリの声。
「待ってなんかないさ」
ヒカリが俺の右隣のスツールに腰かけると、懐かしいシトラスが香った。
それだけで胸はいっぱいであふれてくる。
いますぐ抱きしめてしまいたい。
「乾杯」
華奢なグラスにそそがれたピンク色の液体は、ときめくような色のくちびるに吸い込まれていく。
カウンターにのせられた左手を逃がさないように握り、そのときめきに軽くくちびるを寄せた。
甘く、しびれるようなキス。
「だめだってば、こんなとこじゃ」
「嫌なら嫌って言えよ」
濡れたルビーに俺が映っている。
今度は深く、沈むようにくちづけた。
甘ったるいアルコールが舌先から全身に流れていく。
ヒカリの頬はみるみるピンク色に染まる。
頬どころか、首筋も、胸元も、指も、白い肌はどんどん浸食されていく。
カラン、とグラスが鳴いた。
離したくちびるからはどちらのものかわからない吐息がもれる。
渇いた喉を潤すためにグラスに口をつける。
しかし到底この渇きを癒すことができないことはわかっていた。
もちろんどうすればいいのかも。
俺の右手とヒカリの左手はつながれたままだった。
1年前とちっとも変わっていない。
劣情と愛情でがんじがらめになった重い扉を、ジャケットの内ポケットから取り出したキーで開ける。
1年に1度だけ、俺たちはここで男と女になる。
悪いな神様、今日だけは見逃してくれよ。
#八神兄妹版深夜の真剣お絵描き文字書き60分一本勝負
2015/7/10「七夕」