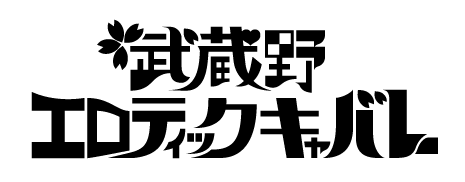甘い罠 蜜をしかける 蟻地獄 ガラスの君が割れるのを待つ
勝手知ったる彼女の家では、僕は顔パスだ。
彼女の母は、タケルくんが来たなら安心ねと買い物に出掛けていった。
彼女の部屋の前まで来ると、吐息のような声が漏れ聞こえてくる。
少しだけ、耳を澄ますと、聞こえてくるのは布がこすれる音と切れ切れの吐息。
彼女が、彼女の大好きな人を想いながら、その身に秘める欲望を発露させているのだろう。
一呼吸おいてからコンコンとノックをすると、ぱたぱたと布団を直しているような音がして、少し笑ってしまった。
うわずったような声でどうぞと言うので、笑いをこらえながらドアを開ける。
「具合はどう?」
彼女の部屋での僕の定位置はベッドの脇だ。ベッドの脚をいつも背もたれにしているから、彼女が背中用のクッションを用意してくれた。やわらかくて気持ちいいからお気に入りだ。
「まだちょっと、だるいかな」
上気した頬は風邪のせいだけではないのだろう。
「起き上がらなくていいよ」
ふとんとパジャマは直しても、髪の毛がくしゃくしゃのままで、そんなところも、たまらなくいとおしい。
「いいの。寝すぎてちょっと退屈だったから」
嘘なんかつかなくてもいいのに。
そういうことを言うと、困らせたくなる。
赤みがかった頬に手を当て、うるんだ瞳をじっと見つめる。そのままキスしたいのをぐっとこらえて、もう片方の手を額に当てた。
「まだちょっと熱っぽいみたいだね」
触れた手から感じる君の体温が、僕以外の人のことを考えて持った熱だということが、余計に僕をたぎらせる。
「誰のことを考えてたの」
離さない。額と頬に添えた手をゆっくりとすべらせて、背中に回す。
「大好きな人のことを、考えてたの」
自分の中から熱が沸き上がる。
嘘をつかないでくれよと思いながら、いざ本当のことを言われると、自分でも制御できない感情に突き動かされる。
「好きだよ」
何もかも、壊して、ぐちゃぐちゃにしてしまいたくなるんだ。
「うん」
か細い声が静かな部屋に響く。
もうこのまま押し倒して好きにしてしまいたいくらいに暴発寸前の僕をとどめたのは腕にこぼれ落ちてきたあたたかな雫だった。
「泣かないで」
君が大好きな人を想って流す涙を、僕が拭ってキスをする。僕たちはそういう関係でいい。
「僕はヒカリちゃんが好きだから、ヒカリちゃんが誰を好きでも、僕のそばにいてくれるだけでいいんだ。いつも言ってるでしょう」
これは甘い罠。君が僕なしでいられなくするための罠。お兄ちゃんのことが大好きな君のことを大好きな僕が、君の恋の受け皿になる。
「嫌いになってくれたらいいのに」
自己嫌悪に陥って、どうしようもなくなって、ぐちゃぐちゃになったところで、僕が君を全部受け止めてあげる。
「僕が?それとも、太一さんが?」
太一さんが君に恋をすることはないように、太一さんが君を、嫌うことなんて絶対にない。
君だってわかってるんだろう。
なのにそういうことを言う。
「嫌いって、言って」
僕が君を嫌いだなんて、どうしたら言えるんだろう。
本当は逆なんだろう。嫌いだなんて言って欲しくないんだろう。本当は、
「好きだ」
って言って欲しいんだろう。僕じゃなくて太一さんに。
ぎゅっと、さっきよりも力を入れて抱き締める。
君を壊して壊して、ぐちゃぐちゃにして、粉々になったところで、僕が君のかけらをひとつ残らず拾うよ。
君とずっと一緒にいるために、蟻地獄に君が落ちて行くのを待って迎えに行くから。
そうしたら君はもう、僕なしでいられない。
火照りの消えない頬に手を当てる。
ゆっくりと、吐息を混ぜ合うように口づけた。
「風邪、引いてるのにごめんね」
言い終わるのがはやいか、今度は君の方から唇を重ねてきた。
「風邪、うつったらごめんね」
自己嫌悪と愛情と倫理観の狭間でぐらぐらしている君は不安定で美しい。
きっと君は、僕の気持ちを利用しているとかって気に病んでるんだろう。
それでいいんだ。気にして、気にして、僕のことを考えて夜も眠れなくなってしまえばいい。
君の罪悪感を利用しているのは、本当は僕の方だよ。