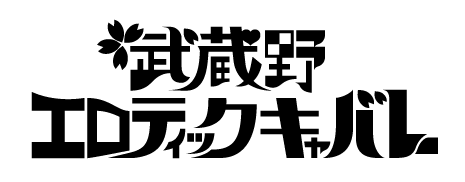閉じ込めて 僕らの恋は悠久の牢獄の中 もう離さない
ねえ、あのおはなしきかせて。竜宮城のおはなし。
またですか?しょうがないですねえ。
昔々のおはなしです。
助けたカメモンに連れられて竜宮城へ行ってみれば、絵にも描けない美しさの少女が僕を待っていました。
渦潮深く潜り込み、鯛やひらめが舞い踊る、夢の楽園竜宮城。
少女はここを治める長、乙姫様でした。
軽く結われた髪には赤い珊瑚をあしらい、豪奢な布を幾重にも纏っており、しかしその身に付けているものに決して見劣ることのない、美しい人でした。
「あなたがカメモンを助けてくれたのね。ありがとう。名前は何て言うのかしら」
「…光子郎と、申します」
「そう、では光子郎殿、どうぞ好きなだけ、この竜宮城でおくつろぎになってね」
長い髪と着物を揺らして乙姫様はしゃなりしゃなりと去っていきました。
僕は、ひとめでこの少女に恋をしたのです。
竜宮城でのもてなしはそれはそれは豪勢なものでした。
食事は普段では口にしないようなものばかり。従者が身支度を全て整えてくれ、そこかしこで美しい舞や歌を楽しむことができました。
乙姫様はカメモンを助けた僕に本当に感謝しているらしく、ちょくちょく僕のところに来ては、感謝の意を述べてくれました。とても素直で可愛らしいひとです。
そして、僕の地上での話を聞きたがりました。
僕はなんでも話しました。
とはいえ、コンピューターのことくらいしか話すことはありませんでしたが、それでもとても興味を示してくれました。
いつの間にか、彼女は僕のことを、「光子郎くん」と呼んでいました。
彼女の繊細な鈴のような声で呼ばれると、自分の名前が今までとは全く違う響きになったような気がしました。
そして彼女は、自分の名前を教えてくれました。
乙姫というのは世襲するもので、彼女のほんとうの名前は「ミミ」というのでした。
僕が「ミミさん」と呼ぶと、彼女は頬を桜貝のように染めるのでした。
僕たちは、恋をしていました。
長い年月が立ちました。ここには時間の概念がなく、僕がどのくらいの時間ここにいるのかはもうわかりませんでした。
僕たちは毎日、おいしいご飯を食べ、美しい舞を見て過ごしました。
その日は、いつもよりも従者たちが慌てていました。
なにがあったのか尋ねても、言葉を濁すだけで何も答えてくれませんでした。
ミミさんの部屋を訪ねると、泣きながら大暴れしていて手がつけられない様でした。
「なんであたしが好きでもないひとと結婚しなきゃいけないの!」
「それが乙姫様の仕事ゲコ…」
「わがまま言わないでほしいタマ…」
「誰が何と言おうと絶対にいや!もう出てって!」
ゲコモンとオタマモンは恨みがましい目で僕を睨みながら、ミミさんの部屋から出ていきました。
「光子郎くん…」
ミミさんは、僕の胸にしがみついて、泣きました。
今まで暴れていたのがまぼろしだったかのように、静かに、かみしめるように、泣きました。
「ミミさん、逃げましょう」
「え?」
「僕と一緒に逃げましょう」
僕はちいさな真珠をひとつぶミミさんに渡しました。
「夜になったら迎えに来ます。誰にも、あなたを渡しません」
夜も深く、何もかもを隠してくれる闇の中、僕はミミさんの部屋に向かいました。
突然、大きな音がしました。なにかが爆発したような、とても大きな音でした。
なにか良くないことが起こっていることだけはわかったので、僕はミミさんの部屋に急ぎました。
「光子郎殿!こんなところにいたゲコ!」
「たいへんタマ!シードラモンが襲ってきてるタマ!」
「シードラモンが?なぜです?」
「それは…乙姫様が結婚をお断りしたから怒ってるゲコ!」
「とにかく乙姫様を玉座に連れてきて欲しいタマ!」
僕はミミさんの部屋に急ぎました。
ミミさんは凛としたたたずまいで珊瑚の椅子に座っていて、その膝には赤い紐できつく縛られた白い箱がありました。
「ミミさん、シードラモンが竜宮城を襲っています。早く、僕と一緒に逃げてください」
くちびるをきゅっと引き結び、僕から決して目を離さずにミミさんは言いました。
「光子郎くん、ごめんね。私、一緒には行けないわ」
張りつめた弦のような声でした。
「こんなことになってしまったの、私のせいなんだもの。私がなんとかしないとだめなの。私はここに残るわ。だから、光子郎くんはひとりで行ってちょうだい。カメモンが地上まで送ってくれるわ」
「そんなこと出来るわけないでしょう!」
ふわりと長い髪が揺れ、ちらりと見えた赤い珊瑚の髪飾りの横には小さな真珠があしらってありました。
「だって!私は乙姫なの!竜宮城の主なの!私がここを離れたら、きっとみんな殺されてしまう。私のせいでみんなを危険にさらすなんて、できない…」
ぽろりぽろりとこぼれる宝石のような涙は、きらめきながら頬をすべって行きました。
「それなら僕はミミさんのそばにいます」
「ありがとう。光子郎くんならそう言ってくれると思ってた」
ミミさんは、膝にのせていた箱を、僕に差し出しました。
「なんですか、これ…」
「開けてびっくり玉手箱よ」
「はい?」
「これを開けると煙が出て、浴びるとおじいさんになっちゃうの」
細胞を衰えさせる揮発性の物質があるとは聞いたことがありましたが、まさかこんなところでお目にかかるとは思いませんでした。
「なるほど、開ければたちまちご老体。ミミさんを愛して幸せなまま、天寿を全うできると言うわけですね」
「光子郎くんがカメモンと一緒に地上に帰るというのなら、それでいいの。私は光子郎くんに生きてほしい。でも、もしも一緒に残るというなら、これを」
「ミミさん…」
「私、光子郎くんと過ごせて、とっても幸せだった」
その瞳は清らかで美しく、主と呼ぶに相応しいものでした。
「おとぎ話のおしまいは、二人は幸せに暮らしました、でしょう?」
なんとかする方法がないか、僕は考えました。
ミミさんとともにハッピーエンドを迎える方法を。
どかん、と大きな音がしました。
ゲコモンやオタマモンたちが、叫んでいるのが聞こえます。
「どうするの?」
僕の心は、決まっていました。
それで、光子郎くんと乙姫様はどうなったの?
それはあなたが一番よく知っているんじゃないですか。
いいじゃない、聴かせてよ。
えーと、僕は玉手箱をシードラモンに投げつけて、その煙でシードラモンは老体になって戦闘不能となり、去っていきました。竜宮城の平和は守られました。
うんうん。
おしまい。
ちょっと!おしまいじゃないでしょ!
えー、僕とミミさんは、えー、いつまでも幸せに、暮らしています。
よくできました。
白い薔薇のように笑って僕の頬にキスをする彼女の指には、小さな真珠の指輪が光っている。
#光ミミ版深夜の真剣お絵かき文字書き60分一本勝負
2015/8/8「童話パロディ」